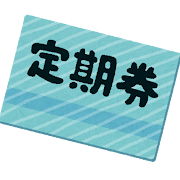
【背景】ウクライナ紛争や中東情勢の影響により、ガソリン価格の上昇に歯止めがかかりません。レギュラーガソリン全国平均は10年前の約120円/Lに対し、約180円/Lに達しています。昨今、社員よりガソリン代を巡る通勤手当の増額要求がなされる事例が少なくありません。
【事例】建設業A社での事例です。往復40キロの距離を自家用車で通勤している中堅社員B男は、「ガソリン代の高騰が生活を圧迫している」と不満を感じています。
ある日、数名の社員とともに、社長に通勤交通費の見直しを直談判しました。支給の根拠となる通勤規程は、10年来、改定されていません。一方的な要求に機嫌を損ねた社長から相談がありました。
【問題点】問題は、経営者も含め社内において、労働法や通勤規程が十分に理解されていないことにあります。まず、労働法には、通勤に要する費用の支払いを、使用者が負担しなければならないとする規定はありません。
つまり、通勤交通費は会社に支払い義務がないのです。実際、30人以上の規模の会社では、約10%が支給していません(令和2年厚生労働省)。次に、社員が「ガソリン代が上がっているから、長年改定されていない通勤規程の金額も上げて当然」、と単純に考えていることと、経営側も支給額を決めた経緯を説明できないことです。
【解決策】早速、解決策を協議しました。全社会議の時に、会社側に通勤交通費の支払い義務はないことと、ガソリン代の金額設定の経緯を正しく伝えることとしました。
【全体会議での対応】全体会議では、ガソリン代から説明を始めました。ガソリン価格は、10年前に比較して約45%上昇する一方で、平均燃費は約40%伸びており、距離単位のガソリン代は10年前と大きな乖離がないこと。
また、実燃費10円/kmに、車両の点検や消耗品の交換費用として5円/kmを加算し、15円/kmとしています。つまり、支給額は負担額より高く設定していることを丁寧に説明しました。B男の場合、1日40㎞の距離に応じた通勤交通費600円に対し、ガソリン代は400円となっていました。
【まとめ】以上のような経過から、新たな対応として、社員の会社への不満をすぐに解消できる外部委託による相談窓口を設置することにしました。会社が定める各種規程は、ルールで縛ることが目的ではなく、心地よく働ける環境整備を言語化したものといえます。これを、第三者から伝えることとしました。
事例のように、会社のルールに多少なりとも不満を抱いている社員は少なくないと思われます。想定される不満要因に対し、早期解消に努めることは何より大切です。労使の信頼関係が揺るがないよう、経営陣は常にアンテナを張り巡らせなければなりません。
第一法規『Case&Advice労働保険Navi 2025年3月号』拙著コラムより転載

