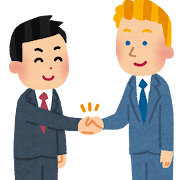
【背景】2024年版『中小・小規模企業白書』によると、1947年~1949年のベビ-ブームに生まれた団塊世代は、75歳以上となり、いわゆる「2025問題」が生じています。
会社経営においては、平均的な引退年齢である70歳を超える中小・小規模企業の社長は245万人います。こうした背景のなか、日本の全企業数の1/3が後継者が未定という、後継者不在の問題に直面しています。
【状況】土木建設業A社の創業社長は還暦を迎え、身内への事業継承かM&Aかを模索していました。ある日、甥B夫(29)が継承の意思を表示したため、急遽、5年で事業継承することになりました。
B夫は、業界未経験者でしたが、意欲は十分です。しかし、前職は全く畑違いの福祉職で、気性の荒い社員の多い建設業への転職に戸惑うことばかりでした。
1年経過しても、先代からの社員が2代目を見る目は厳しく、指示通りに動きません。何かにつけ「先代はこんな指示はしなかった」と反発されました。付け入るスキを与えてしまったため、社員のわがままな要求もエスカレートしていきました。
例えば、人手が足りなくても厳しい気候の時期、相談なく長期休暇の取得を強行する社員が出てきました。B夫は、精一杯会社に尽くしているつもりですが、社員の心はついてきません。ついには、社長を辞めたいと口走るようになりました。
【問題点】B夫の問題点は、主に3つ考えられました。
1つは、先代の組織をそのまま引き継ごうとしていることです。先代と2代目は別人格なので、経営スタイルや組織をそのまま引き継ぐには無理があります。
次に、対人関係スキルが未熟なことです。社員や取引先などと十分なコミュニケーションを取れていませんが、解決方法がわからないままでいることです。
3つ目は、最も大切なことですが、覚悟が足りないことです。疑問や不安な点を整理し、課題を1つ1つ解決する、すぐに解決できなくても相談先を決める、といった取り組みが求められます。見通しが立てば困難のなかでも前に進む胆力が備わります。戦略のない状況では、先が見えない不安に押しつぶされそうになるばかりです。実際、B夫は、社員とその家族の生活、会社の将来について、適切な決断を下す場面が連続し疲弊してしまっていました。
【解決策】先代、B夫と協議した結果、次の指針で進めながらB夫の覚悟を促すことにしました。
①先代社長を意識しすぎないこと。
先代社長が築いたものをそのまま継承できるなら、社員や対外的に信頼を築くことはできます。しかし、先述した通り、先代とは人格も異なるため、全く変化のない継承は不可能でしょう。仮にそのまま継承すると、変化が求められるビジネス環境に後れを取る可能性があります。
②自分のビジョンを掲げ理想の組織構造を考えること。
ビジョンは、組織の将来像や方向性を示すものであり、B夫が組織をどのように築きたいのかを伝えることができます。ビジョンを持つことで、組織の方向性が明確になり、社員や取引先は共通の目標に向かって協力しやすくなります。
③右腕となる人材を周囲に配置する。
何でも相談でき信頼できる、メンター、専門家、他の経営者との連携は、経営者の孤独を癒し、成長を促します。B夫は、知識や洞察力を高めるために、彼らと意見交換をすることで、新たな視点やアイデアを得るなど道を切り拓きやすくなるでしょう。
【経過】先代や専門家が協力する姿勢をみせたことで、B夫の表情は明るくなりました。周りに支えられ、様々な課題はあるものの、少しずつ解決に向かっていることで安心したのでしょう。
【まとめ】2代目への事業のバトンタッチは、社員とその家族、取引先などの生活に大きな影響を与えます。B夫と同じ悩みを抱える後継者も少なくありません。2代目が問題点を一人で抱え込み精神的に疲弊してしまわないよう、早期に先代を含む専門家がアシストし解決していく体制づくりが不可欠です。
【経過】先代や専門家が協力する姿勢をみせたことで、B夫の表情は明るくなりました。周りに支えられ、様々な課題はあるものの、少しずつ解決に向かっていることで安心したのでしょう。
【まとめ】2代目への事業のバトンタッチは、社員とその家族、取引先などの生活に大きな影響を与えます。B夫と同じ悩みを抱える後継者も少なくありません。2代目が問題点を一人で抱え込み精神的に疲弊してしまわないよう、早期に先代を含む専門家がアシストし解決していく体制づくりが不可欠です。

