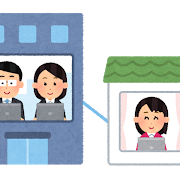
【背景】
新型コロナウィルス感染症(以下「コロナ」という)が、5類に分類され2年が経過しました。『パーソナル総合研究所』の2025年7月の調査では、テレワークの実施率は22.5%にとどまり4割近くが実施頻度が減少したと回答しています。
意思疎通が難しいなどの理由で、在宅勤務から出社に切り替える企業数は増加する一方で、テレワーク実施者の8割強が「続けたい」「やや続けたい」と回答しています。
「エン転職」の2023年8月の調査では、出社頻度は転職活動における企業選びにどの程度影響するかを尋ねると、「とても影響する・やや影響する」と回答した方は6割を超えるといったデータもあり、社員に心地よく働き続けてもらうためには「在宅勤務」は避けて通れない状況です。
【相談】
コロナを機に、事務職社員を在宅勤務に切り替えていたA社からの相談です。システムの大幅入替えに伴い、在宅勤務中のB子に、出社勤務に切り替える旨を伝えたところ、「在宅勤務は労働者の権利であり侵害するとは何事か」とクレームを入れてきました。B子に気圧され、困った人事担当者から相談がありました。
【状況】
B子は日本でコロナが表面化した、2019年12月の直前に入社しました。「会社への出勤」を前提とする雇用契約書を締結していましたが、2020年4月の緊急事態宣言の発令以降、在宅勤務を命じられました。B子は、保育園に通う幼児を抱えており、コロナ収束後も続く在宅勤務は、B子にとって有益な働き方でした。
【問題点】
法的な手順を踏むなら、在宅勤務に移行する際に対象社員へ「在宅勤務命令書」を渡すことが最善策となります。この書面には、在宅勤務期間や勤務場所を指定し、業務命令で解除が可能であり出勤に切り替える旨を明記、社員からは、署名捺印をもらいます。しかし、未曽有のコロナ拡大により、特に中小企業では社内の感染拡大を防ぐことに奔走するだけで手一杯となり、在宅勤務に関し書面を交わすことなど思いもよりませんでした。
【解決策】
B子の主張への対応を協議しながら、次を確認しました。①在宅勤務は、労働基準法や労働契約法などの法律上の義務ではなく、導入は会社の裁量で行える制度であること、②在宅勤務は通勤時間を省く、子育て上のメリットがある一方で、情報漏洩リスクやコミュニケーション不足、生産性管理の課題などリスクを伴うこと、③譲歩案として、在宅勤務やフレックスタイムを導入する職種を増やすなど、社員が働きやすい環境整備に努める旨を伝えること――。
【経過】
直属の上司が状況を説明しても、B子は、今まで認められていた在宅勤務が急に否認されることに合点がいかない様子でした。そこで、B子の立場に理解を示しながら、部長から次のように伝えました。――在宅勤務は、通勤の負担なく集中しやすい環境であり、今更変えろと言われても簡単に戻れない事情であることはわかる。ただ、会社が制度として設けるもので、法律上“当然の権利”ではない。
一方で、できる限り社員の声を反映したいので、どういう形なら労使双方にとってメリットがあるのか一緒に考えたい。まずは、システムの入替をスムーズに行い、業務効率化を図ることで在宅勤務の促進に繋がるように協力してもらえないか、と。
部長が、子育て世代への理解を示しながら、在宅勤務を廃止するわけではないと伝えたことで、B子は状況を慮ってくれたと感じたようです。出社勤務に納得してくれました。
【まとめ】
在宅勤務は、コロナ禍の臨時措置であり、コロナ収束後は会社の判断で出社に切替えることが出来る旨、書面で残すべきでした。しかし、前例のない事態に、法的整備に手が回らなかった会社も少なくないと思われます。
今回は、社員の立場を理解し譲歩案を打ち出すことで、労使双方のわだかまりをなくすことができました。会社側が社員の生活環境をも把握し尊重する姿勢を示すことは、労使間の信頼を築くうえで不可欠なものだと感じる出来事でした。
第一法規『Case&Advice労働保険Navi 2025年9月号』拙著コラムより転載

